
2025年3月28日、慶應義塾大学SFC研究所「みらいのまちをつくる・ラボ」は、「第6回 Oimachi Research Forum 〜歩きたくなるスマートシティ大井町の取り組み〜」(ORF)を開催しました。当日は74名の方にご来場いただき、官・民・学が連携しながら大井町の未来像を共に描く場となりました。本記事では、その開催レポートをお届けします。
これまでORFは、本研究所の年度末成果報告会として実施してきましたが、今回は2024年度より始動した東京都の補助事業「デジタルエリアデザインの共創 in 大井町」プロジェクトの報告会も兼ねて開催しました。イベントは、セッションとオープン展示の二つのプログラムで構成され、セッションでは「歩きたくなるスマートシティ大井町の取り組み」というテーマのもと、東京都・品川区などの行政関係者、地域企業、地元NPO、大学研究者など多様な登壇者をお迎えし、それぞれの立場から実践と構想を共有いただきました。またセッションと並行して、SFC研究所が今年度に大井町で取り組んできた研究・実践活動を紹介する常設のオープン展示スペースも設け、来場者との活発な対話が生まれる場となりました。
展示のテーマや登壇者の資料は、こちらのページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
【セッション1】「地域主体によるスマートな大井町に向けての取り組み」

セッション1では都市政策・地域住民・研究者の視点から、デジタルとアナログ、制度と実践、個人と都市といった多層的な議論が展開され、スマートシティとしての大井町の未来像が描かれました。それぞれの発表を、登壇者ごとに紹介します。
■「スマート東京の推進について」
巻嶋國雄(東京都 デジタルサービス推進部長)
東京都が進める「スマート東京」構想の概要と、都が推進するオープンデータの利活用や、地域課題に即したデジタル技術の導入、補助金制度の活用可能性についても詳しく解説がありました。
(参加者の声)
・デジタルのチカラで都民のQOL向上に期待している
・東京都が積極的にオープンデーターの活用推進していることが解った
・行政がリーダーシップを取っており素晴らしい取り組みだと思う
■「大井町駅周辺のまちづくり」
佐藤健二・落合純也・土屋那家久(品川区)
品川区が進める大井町駅周辺の再開発構想について、都市基盤の整備と住民参加のバランスに注目した取り組みが紹介されました。駅前の空間再編、交通・歩行環境の改善、市民協働の可能性など、行政がリードするまちづくりの姿勢が示されました。
(参加者の声)
・プラン自体は良く出来ている。積極的に外部と交流した方がいい
・大井町の発展に期待している
■「地域住民主体のまちづくりin大井町」
後藤邦夫(NPOまちづくり大井 理事長代理)
長年にわたる地域住民によるまちづくりの実践例として、NPOまちづくり大井の活動内容が紹介されました。イベントの企画や、地域ニーズの収集と反映といったアプローチが、行政や研究機関と連携しながら推進されていることが語られました。
(参加者の声)
・地域住民の細かな意見が反映されるまちづくりを期待している
・大井町らしい独自の良さを出してほしいと思った
■「歩いて暮らせるまちづくり」
尾崎信(東京大学大学院サステナブル社会デザインセンター 特任研究員)
空間と身体の関係性に注目した研究の視点から、「誰もが歩きやすい都市」の条件とその実現手法について提言がありました。空間デザインには日本全国の事例を紹介いただきました。
(参加者の声)
・歩いて暮らせるまちは素敵だと思う。誰にでもやさしい(子供やシニアも障害を持つ人)まちをぜひつくってほしい
・大変参考になった。行政と地域の組織が協力がしっかりしているように感じた
■「デジタルエリアデザインin大井町の取り組み」
厳網林(慶應義塾大学 環境情報学部 教授)
人流データ・地理情報・地域属性などを掛け合わせ、まちの特徴を“可視化”する「デジタルエリアデザイン」の研究成果が紹介されました。住民参加型で進められたウォーカビリティ評価のプロセスや、ダッシュボード化による活用事例など、実証的な研究の進展が報告されました。
(参加者の声)
・大井町の魅力を地元の方々・学生さん・自治体含めた官民学の集大成となってつくりあげることを実現化したことはすばらしい。特にデジタル化した「まち」の可視化については常にアップデートされており、次のステージが楽しみだ
・歩きやすさに対する多角的な視点が大変勉強になった
【セッション2】地域共創ネットワーキングの取り組み

続いてのセッションでは、SFC研究所と地域のプレイヤーが登壇し、多様な実践報告が行われました。それぞれの発表を、登壇者ごとに紹介します。
■「学びのコミュニティ〜ミドル・シニアのつながりをどうつくるか〜」
河野純子(慶應義塾大学SFC研究所)
大井町コミュニティキャンパスプロジェクトの一環として、中高年会社員のセカンドキャリアを支援する「ミドル・シニアの起業研究会」の取り組みが紹介されました。2024年度にはリアルイベントが開催され、活動成果として参加者から寄せられた声や気づきが共有されました。
(参加者の声)
・ミドルの心理課題をわかりやすく解説くださり、内容となり大変勉強になった
・これからのまちづくり・コミュニティづくりの大きな柱の一つと認識した
■「大井町ミライを共創するネットワークづくり」
矢後真由美(株式会社Teable)・濱田健太郎(株式会社Neeew Local)
地域内外のネットワークを育みながら、大井町の未来を地域プレイヤーと共に描いていく取り組みが紹介されました。地域商店街や東京商工会議所との連携、地方都市との協業事例など、複数の接点を持つプロジェクトの広がりが語られました。
(参加者の声)
・実践者の具体例には重みと凄みがあった
・地道に活動してきているので、サポートしていきたい
■「ウェルネス向上のためのスマートグラス実証実験」
小池悠也(株式会社dendrite)
スマートグラスを活用した歩行者の視線・姿勢データの取得と、それを健康促進や街の設計に応用する実証実験の取り組みが紹介されました。短期間で実践と検証を行う手法や、技術とまちづくりの融合可能性が注目されました。
(参加者の声)
・健康な大井町というコンセプトもいいのでは
・動いている人の方がスマートグラスとの相性がいいというのは、目からうろこだった
■「人をつなぐHOPEプロジェクトの取り組み」
年森慎一(みんなのクリニック大井町)
診療所が地域住民の健康と孤立の両面を支える拠点として機能することを目指す「HOPEプロジェクト」が紹介されました。医療現場と地域が交わることで、安心して暮らせるまちづくりの基盤づくりに取り組む姿勢が伝えられました。
(参加者の声)
・あらゆる年代と関連づけられそう
・いい取り組みだと思った
■「スマートシティ支援プラットフォームの検討」
安田章展(アドソル日進株式会社)・中山俊氏(慶應義塾大学SFC研究所)
多様な都市課題に対応するためのスマートシティ支援プラットフォームの構想とその設計思想が紹介されました。企業や自治体とのデータ連携を前提に、可視化・分析・政策立案支援までを視野に入れた実装方針が語られました。
(参加者の声)
・実績をアピールし、データを活用する企業や組織が出て来て欲しい
・しっかり取り組んでいると思った
■「GeoAIツールの開発と大井町での試み」
大場章弘(中央大学中央研究機構 助教)
地理空間情報とAI技術を融合させた「GeoAI」ツールの開発と、その大井町での実証事例が紹介されました。都市の特性や歩行傾向などの可視化を通じて、まちづくりにおける意思決定支援の新たな可能性が示されました。
(参加者の声)
・パワフルな地理情報の社会実装への意気込みに感銘をうけた
・これからのAIツールの開発が進みます事期待している
【オープン展示】SFCのみらいのまちへの取り組み
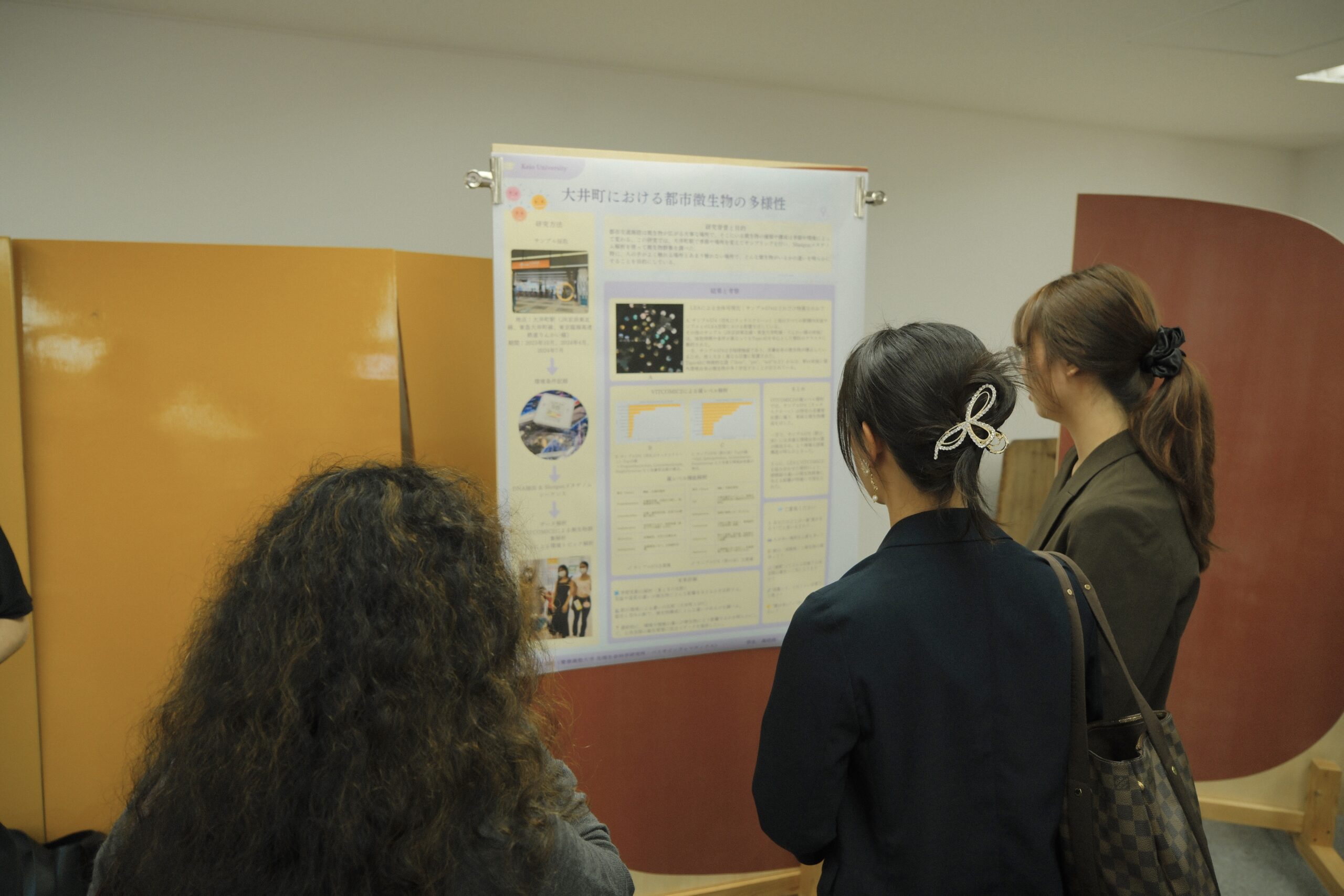
常設のポスター展示には、SFC研究所による多様な取り組みが並び、来場者と学生・研究者の間で自然と対話が生まれていました。
(参加者の声)
・とても充実していた
・ポスター展示の配置などが効率的で分かりやすかった
・画期的がみなぎっており、もっとじっくり一つ一つのブースでお話をお伺いしたかった
こうした声は、今後のプロジェクト展開においても重要な指針となります。
おわりに
レポートは以上です。本イベントにご関心・ご協力いただいた参加者・登壇者の皆様、誠にありがとうございました。今回のネットワーキングと対話を起点に、SFC研究所「みらいのまちをつくる・ラボ」は今後も、地域とともに大井町の未来を探求していきます。
