慶應義塾大学 國領二郎教授が語る「品川愛」と未来へのまちづくり—「みらいの大井町をつくる・ラボ」(FMしながわ)第60回放送レポート

「FMしながわ」では、2020年4月より、慶應義塾大学、飯盛義徳研究室・大井町元気プロジェクト所属の学生によるレギュラー番組『みらいの大井町をつくる・ラボ』が放送されています。コンセプトは、大井町や住民の方の「いま」と「みらい」。大学生ならではの目線から大井町の魅力や可能性、住民の方の生の声を発信しています。
3月5日(水)18時から、第60回目が放送されました。パーソナリティーは、宮西惟成(4年)、坂本壮凛(2年)、水上晶愛(2年)の3名です。
■3月の放送内容
1.<オープニング>
今回は春休み期間中の収録ということで、パーソナリティの3人はそれぞれ大阪、那覇、東京と、異なる場所からオンラインで収録を行い、特別な形での放送となりました。
2025年度の抱負という話題では、水上さんは「正直でいたい」と素直な気持ちを語り、坂本さんは「愛されるプロジェクトをつくりたい」と意気込みました。4年生のため3月に卒業を控えた宮西さんも「これからはリスナーとして番組を応援したい」と語り、お便りの募集も呼びかけました。
2.<みらい対談>
続いてのコーナーは、大井町への思いや、ゲストの思い描く未来についてお話を伺う、「みらい対談」です。今回は、慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎(こくりょう じろう)先生にお話を伺いました。
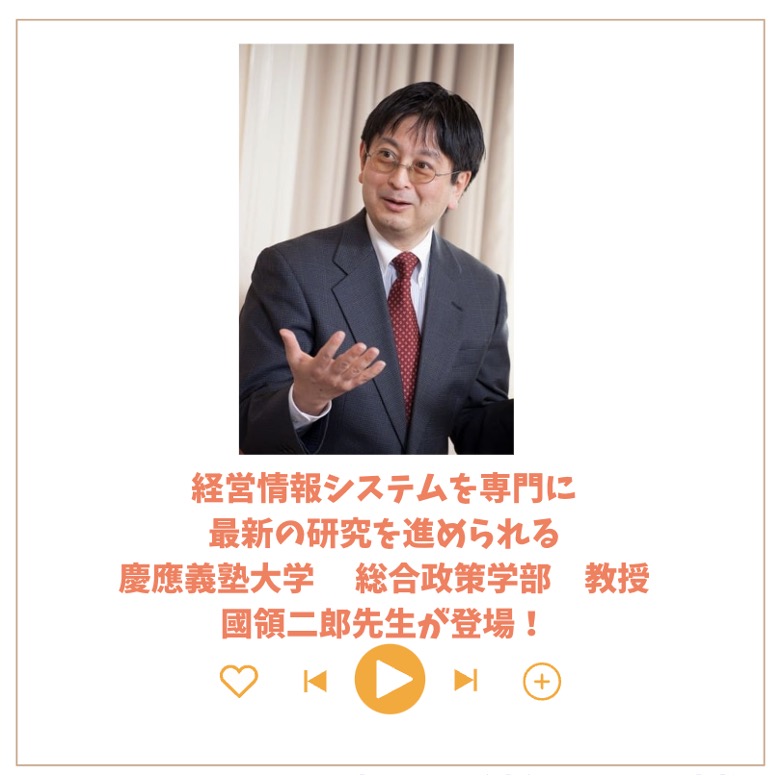
Q.自己紹介をお願いします。
國領先生:自己紹介をする前に、1つ強調しておきたいのが、私は品川区をとても愛している人間だということ。去年まで品川区に住んでいました。それが人生2回目の品川区在住で、高校の時に五反田で乗り換えて大田区に住んでいたころを含めると、かなりこのエリアには思い入れがあります。
私自身は慶應義塾大学の教員をしていて、まもなく定年退職を迎えます。情報技術とビジネスの分野で研究や教育をしてきた人間です。よろしくお願いします!
Q.今まで取り組まれてきた研究テーマと内容について教えてください。
今最大のテーマは特にまちづくりにおいて情報技術を活用する際に、どのような情報基盤を作ればいいのかということです。最近のネットは便利になった反面、間違った情報や時にはサイバー攻撃など怖いことが起こったりします。
そのような状況下でセンシティブな情報も活用して世の中をより良くするには、きちんとしたインフラを整えなければなりません。街の中で、例えば、助け合いみたいなことをやろうと思っても、相手が信用できるのかよくわからない、とか、掲示板を開けてても荒らしがいっぱい来るとか、そういうことが起こらずに上手に活用できる、そのような環境の実現に向けて研究しています。
Q.情報技術とビジネスの領域に興味を持ったきっかけはなんですか?
國領先生:それは、大学生の時にインターンシップでアメリカへ行った際の出来事です。インターネットがまだ世の中であまり知られていない頃、アメリカではコンピューターを通信回線に繋いで、様々なことに活用し始めていました。その光景を目の当たりにして、大学生ながら「これは世の中を変えるな」と思い、就職活動もその分野を目指したことがきっかけです。かなり先見の明があったと自分でも思っています。
Q.インフラや情報基盤という観点で今の品川区をどう思われますか?
國領先生:都会はどこでも5Gに繋がったり、品川区にはケーブルテレビがあり、結構インフラは整っていると思います。その上で、便利な分だけそれを活用して、ローカルコミュニティでいろいろ活動しようと考えると、課題も大きいですよね。その中でも、コミュニティ感覚のようなものをどのようにして大都会の中で作り出していくかが大きな課題になると考えています。
Q.ラジオなどのメディアをどのように活用していけばいいと思いますか?
國領先生:ラジオの中でも特にFMというのは、電波の届く範囲を狭くすることが可能です。その中で、すごくローカルな情報をみんなで共有することができるという意味で、非常に大事なメディアだと思います。
坂本:今のお話を聞き、なるべく私たちの番組でも大井町や品川区のエリアに密着した番組制作を今後も続けていきたいなと思いました。
Q.ずっと学生と関わってきた中で、「学生の変化」を感じたことはありますか?
國領先生:学生の変化は感じてきました。特にコロナの時期は縦や横の交流が減っていたと思います。例えば、宴会の幹事のやり方です。そういうのは先輩から後輩に引き継ぐものだと思いますが、先輩が分かっていないから、後輩も分からない、という事が、いまだに少し引きずっていると感じます。
宮西:そうですね。どう先輩と接していいかなど、そういうコミュニケーションの取り方のようなものは、最初の頃苦労した部分です。
國領先生:ですよね。僕らにとってみると、3〜4年は人生の20分の1ですが、君たちにとっては10分の1どころではないはずですよね。5分の1くらいだからこそ、インパクトが大きいですよね。
Q.コロナ禍の授業中ではどのような工夫をされていましたか?
國領先生:コロナが突発した時は慶應義塾大学の情報基盤担当で、大変でした。オンラインで授業をする事が決まり、4〜5週間の間に慶應全体で何万という科目を全てオンラインに移行させないといけませんでした。
宮西:大変な時期でしたね。
國領先生:オンラインへ移行する時期になり、その時に初めて「zoom」を知る先生や学生が大勢いました。そのような環境の中、オンラインへの移行を行いました。zoomはまだ簡単でしたが、それ以上に履修申告のシステムなども、デジタルに移行しないといけなかったので、非常に大変でした。
坂本:想像しただけで、お腹が痛くなってきます。
國領先生:その時、つくづく思ったのは、やはり現場の人のクリエイティビティや底力みたいなものです。普段文句を言っている学生や先生が、「もう、これをするしかない!」というような逼迫した状態になると、みんなで助け合いをしてなんとかしてしまう、そういう底力を見せてくださったのが印象に残っています。
宮西:学生にとっても、コロナ禍は大変だったと思いますが、先生方にとってはさらに大変だったということを、お話を聞いていて思いました。教員として、大変だったことや、乗り越えないといけない事がさまざまあったと思います。
Q.教員をやっている中で、やりがいや、すごく嬉しかったエピソードなどはありますか?
國領先生:それはやはり学生の皆さんが、様々な方面で活躍されることですね。それだけではなく、チャレンジすると失敗することもありますが、失敗した時にお互い助け合ってなんとか乗り越えていく、そういう姿が見れると、とても嬉しくて、教員という仕事はとても贅沢だなと思っています。
Q.学生たちにメッセージをお願いいたします!
國領先生:この時代、いろんなチャンスに溢れていると思うので、ぜひいろんなことに挑戦していただけたらと思います。どうせうまくいかないよ、どうせだめだよ、とこの10年くらい、負け犬根性がついてしまったようなところがあるように感じます。しかし全くそんなことはありません。ぜひ、いろんなことに挑戦していただけたらと思います!
3.みらいの部屋
このコーナーでは大井町の最新のニュースや課題を一つ取り上げて、みんなで一緒に、未来の大井町について考えていきます。今回はみらい対談に引き続き、國領先生と共に「街の変化」をテーマに大井町の今後について考えていきました。
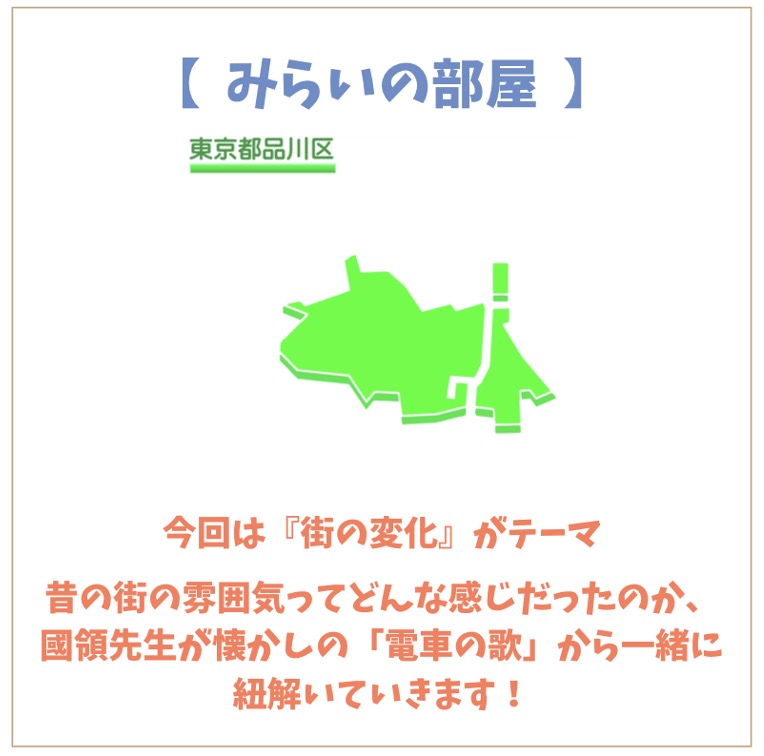
坂本:國領先生は品川区で今まで2度暮らしていたことがあるとお伺いしました。最初に品川に住んだときはどのような経緯だったのでしょうか?
國領先生:就職して、とても忙しい昭和のような働き方をしていた頃です。結婚して独立しないといけないとなった時に、都心へのアクセスが便利なところを考え、戸越銀座のそばに住みました。その頃の品川区というのは、まだ工場がたくさんあり、非常に庶民的な雰囲気がありました。品川区は東京の中でも歴史が長くある街なので、昔から住んでいる方や私のように通勤する人が混在している街です。いまだに戸越銀座といえば、まさに商店街というようなところがあり、賑わっていて、楽しい街だなと思っています。
坂本:その後一度他の場所に転居されて、再び品川区に帰ってこられたということですよね。
國領先生:海外へ留学にいくため、品川区から一度出ました。その後しばらく間が空いて、5年前から去年まで住んでいました。
宮西:最初生活されていたのは、20代くらいだと思うのですが、その時に見ていた戸越銀座の付近と最近で、街の景色や変化は、國領先生の中でどのように映りましたか?
國領先生:工場みたいなものは無くなってきていて、商店街もまだまだ個人商店が残っていますが、だいぶチェーン店が増えてきていますよね。正直に言うと、少し東京に飲み込まれている感じがしました。今回は五反田に住み、そのような感覚を持ちました。なんとか、あの雰囲気を残せたらいいなと思いましたね。
宮西:5年前にもう一度品川区に戻ってこようと思ったのは、何か気持ちの中できっかけがあったのですか?
國領先生:留学から帰ってきてからはしばらく世田谷に住んでいました。理由があり、家を別途探すことになり、品川区が良かったので、再び行こうと思いました。五反田あたりは、どちらかというと目黒川が氾濫する場所というイメージがありましたが、最近は氾濫しなくなり、すごく綺麗で、タワーマンションが立ち並んでいます。この変化にも非常に驚いています。
坂本:品川区に限ったことではないと思いますが、チェーン展開しているお店が増えると、だんだんと日本全体で街の見え方が似てくるところがあると思います。大井町や品川区も、今後街の個性を取り戻していく段階に入っていくのかなと思っていまして、そういう時に何か改善できるヒントやアイデアなどありますか?
國領先生:品川区は歴史のある街なので、その歴史の中には、少し暗めの歴史もあるかもしれませんが、それも含めて、今までの歴史を大事にしながら、まちづくりに反映させていくのが良いと考えています。今大井町で大開発をしているところなので、よくよく考えて、新しく歴史を活かすような発想で考えていただきたいと思います。
宮西:工場が少なくなり、東京に飲み込まれてたようで少し寂しいと思うというお話でしたが、反対に、こういう点が良くなったなというポジティブな変化はありしましたか?
国領先生:今申し上げたようなことを考えていらっしゃる方がいるのではないかと思います。京浜急行や東海道のあたり、筑波町など、そういうような考え方で、演出していこうという事が見てとれると感じます。歴史的なものも掘り起こしていきながらというところが見えるので、そういう動きを大事にしていくと良いと思います。
宮西:ありがとうございます。これまでのお話いただいたことと質問の毛色が変わるんですけども、今回曲のリクエストをお願いした際に、電車の歌をいくつかリストアップして下さいました。そのような電車の歌にまつわるエピソードをお聞ききしたいです。
國領先生:リクエストして、残念ながら流せなかった曲がいくつがありました。そのうちの一つが、「目蒲線物語」で、これが冒頭で申し上げた品川愛に溢れているけれど、それを自虐的に歌っているみたいなものです。目蒲線というのは通っている部分の大体が品川区なのですが、「あってもなくても、どうでもいい、目蒲線」という歌詞があります。この歌詞からは、そのようなことが言われているが、田園調布も通っているんだぞ、みたいなものを感じます。
もう一つ、「品川心中」という落語で有名なネタを元にした曲をリクエストしていました。お染という宿場花街で見栄を張っている人がいたのですが、花街でもトップの花魁から、だんだん落ち目になり、見栄を張りきれなくなってきました。そして心中しようと思い、男を騙して、心中に引きずり込もうとしたのですが、最後の土壇場で、お金を出してくれる別の旦那が見つかるんです。だけどその時には心中の相手の男は死んでしまっていて、ごめんねという、ひどい落語でひどい曲なんですけども、それを笑わせるように歌ってくれる話なんですね。
こういうのがある種、品川の歴史や心を反映していると思っています。したたかさや、たくましさを考えさせてくれるものです。その中でも「目蒲線物語」は先ほどの池上線の、ドアの隙間から寒い風が吹いていて、心も寒いんだと、同じような心意気を感じますね。
宮西:品川区で長く生活していたからこその、國領先生の熱い品川区への想いを感じる事ができました。品川区についてこれまでなかった角度から、新しいことを知ることができたと思います。皆さんもぜひ、品川区について長い歴史をもとにしながら、大切にしてきたものは何か考えてみてはいかがでしょうか。
4.エンディング
今年度最後の放送になりました。國領先生は今回の放送を振り返っていかがでしたか?
國領先生:品川区をネタにして話すというのは生まれて初めてで、どんなことを話そうかと思い、色々考えるうちに、僕はやはり品川区のことが、とても好きなんだなと改めて感じさせていただきました。とてもいい機会になりました。感謝しています。加えて、学生の諸君が地域にこのように関心を持ちながら、番組を作る中で新しい発見をしたり、未来について考えていることをコミュニティに向けて発信していることは、大学の教員としても、非常に嬉しいことです。今回は大変いい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。
宮西:そう言っていただけて、とても嬉しいです。私は4年生ですのでこの3月で卒業しますが、来期からは坂本さんと水上さんを中心に、また素晴らしいメンバーで放送を作ってくれると思うので、新しいみらいの大井町をつくる・ラボが楽しみですね。
坂本:今回は、改めて品川区の歴史を國領先生と考えることができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございます。
水上:大井町は歴史があるというところで、他の地域の曲も調べてみたいなと思いました。
坂本:いろいろな地域の曲を集めてみるのも面白そうですよね。
宮西:放送の中でも地域に特化した曲を流すことで、新しい発見や曲の中で書かれている世界観を体感することができました。地域がこれまで歩んできた歴史だったり、地域の人々にどう愛されてきたのか、今回歌詞を見て、感じることがあり、非常に面白かったですね。
坂本:タイムカプセルですよね。
水上:確かに!
宮西:気持ちが眠っているのが曲なのかもしれないですよね。新しい視点で大井町を紐解くことができ、自分も新しい視点を持ったまま、最後の放送を迎えることができて、良かったです。
■今回放送した楽曲
・OPテーマ:あいみょん 『ハルノヒ』
・レミオロメン『3月9日』
・西島三重子『池上線』
・手島葵『テルーの唄』
・YOASOBI『ハルカ』
次回、第61回放送は、4月2日(水)18時〜です。番組では、リスナーの皆さんからのおたよりを募集しています。
X(旧Twitter)アカウント:@oimachi_lab
公式ハッシュタグ: #大井町ラボ
番組の感想やメッセージ、要望、アイデアなど、どしどしお送りください!
(レポート/慶應義塾大学 総合政策学部2年 水上晶愛)
